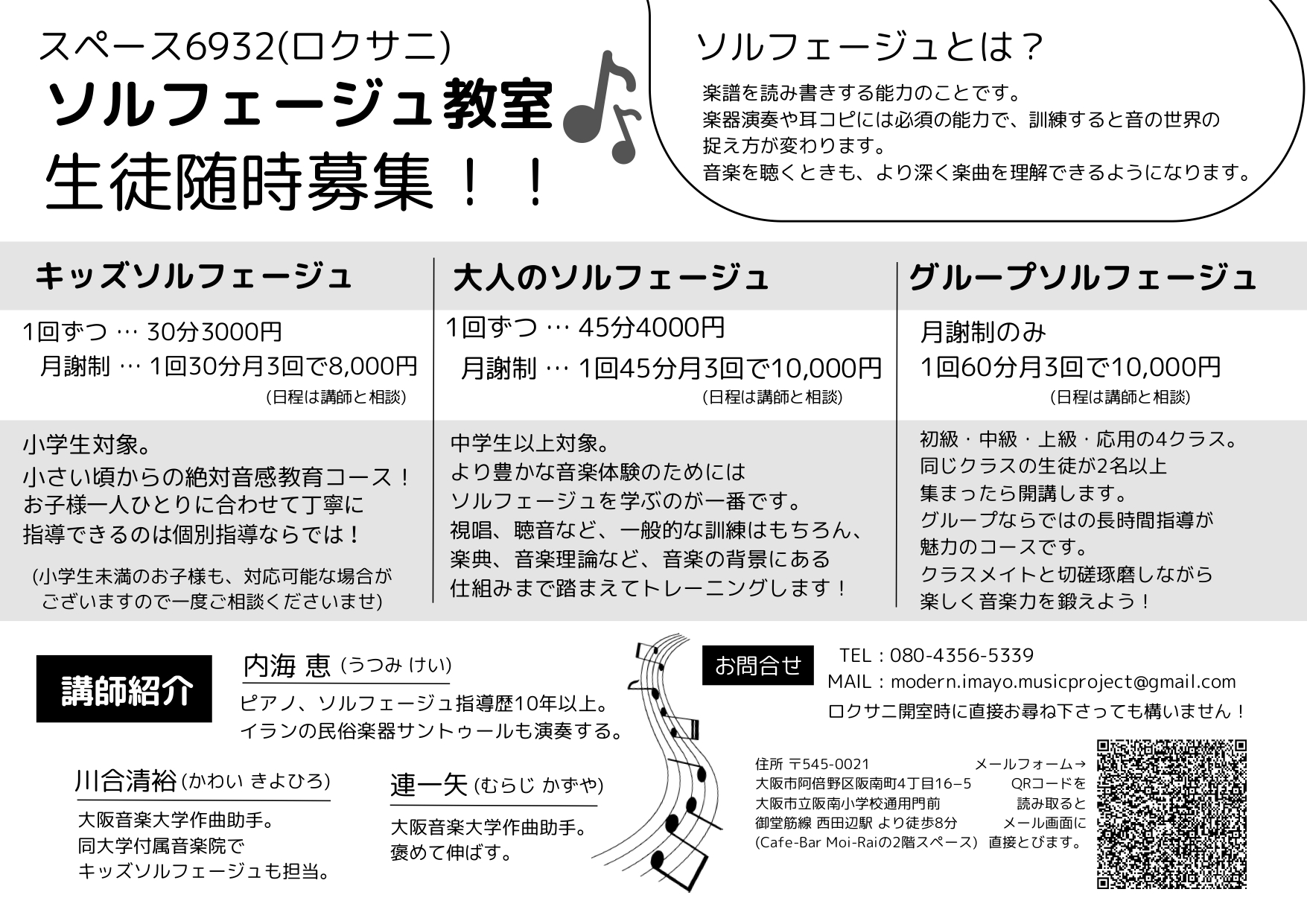ざわめきに耳をすますとき~ソリッドな視覚とリキッドな聴覚~
ここ2、3日、視覚と聴覚について考えている。
田村正和の訃報の記事を見て、ついつい「古畑任三郎」シリーズを見ていたときのことだ。このドラマは音楽も秀逸だけど音楽が使われる場面は限られていて、ほとんどは古畑と犯人の会話がメインなので、楽器を練習しながら見るのにちょうどいい、ということに気づいた。
余計な効果音がないので、音を鳴らしながら見ても混ざらないので練習にもテレビにも集中できるのだ。(!)
ただ、練習する楽器は弦楽器や太鼓、、私にとってはウードとトンバクがベストだ。
(たぶん笛もできるだろうけどさすがに気が散る気がする。あとはギターもいける思う。)
でも、ピアノやサントゥールでは「ながら練習」は難しい。
この違いは「視覚」を使うかどうかにある、と気づいた。
そもそも、ウードやトンバクは演奏中に自分の手が見えない。特にウードは全然見えない。
頼りになるのは「聴覚」と「触覚」で「視覚」はあまり必要ないということになる。
でもピアノやサントゥールでは鍵盤や弦の多さ、そして手元が見えるという点で、どうしても「視覚」に頼ってしまう。
一生懸命手元を見て、そして楽譜も見て、、目に頼りすぎるあまり、皮膚感覚と耳を鋭敏にして、豊かな音色を作ることがおろそかになってしまうことはよくあることだ。ピアノにおいて、曲の音作り、音色作りはある程度弾けてから、最後の段階とされることが多い。ほんとは一番最初にやるべきなのに!自らも省みて反省する。(でもたぶん昔の音楽家にはこんな逆転現象は起こらなかったはずだ。少なくとも五線譜が開発される前までは。)
「視覚」というと、私にはソリッドなイメージがある。
自分と対象の間には距離があり、分離している。それぞれは別物で混ざり合うことはない。
美術館で作品を鑑賞するときのような感じだ。
モナリザの微笑みと対峙する美術鑑賞者。
見る、という行為にはどこか対象を分析するとか、コントロールしようとする感覚がつきまとうな感じがする。
(出会った人の顔を見て、美しいかどうか判断する、など。)
主導権を握っているのは常に「私」であり、見られる側は沈黙している。
一方、「聴覚」は私にとってリキッドなイメージである。対象となる音と「私」は分離せず、距離は無くなり溶け合う。そして、やがてここにある「私」の輪郭さえあいまいになってしまう。私という存在は音と混ざり合い拡張し、世界に向かって拡散されていき、ついには全て溶けてしまう、、というイメージだ。
ただ、クラシック音楽ではそういう「溶け合い」の度合いは少なくなるかもしれない。(もちろんあることにはあるが。)
音楽鑑賞という特殊な環境下においては。知っている曲目ならなおさらだ。あらかじめ「知っている」音を聴くという、聴覚体験の中ではかなり特異な状況になってしまう。それは自然界や生活の中で現れる予期せぬ音、ノイズを聴くのとは違う。
クラシック音楽を聴くときには、美術鑑賞をするときのような「観察者」としての位置に我々は置かれる、、、話が脱線しそうだ。
「音楽へのまなざし」という一見矛盾したテーマも面白いが、今回は音のリキッドな特性に注目したい。
視覚と聴覚についてを深く考え始めたのは、兵藤裕巳の『琵琶法師―〈異界〉を語る人びと』という本を読んだからだ。
「耳無し芳一」の話から始まるこの本は、目が見えないからこそアクロバティックに様々な世界(そこには現実以外も含まれる)にアクセスできる琵琶法師のシャーマニスティックな特性について詳しく説明されている。
目を閉じると今までに聞こえてこなかった音が聞こえてくるようになる。
盲目の琵琶法師や、三味線弾き、共同体から外れたところに位置するさすらいの旅人が楽器を抱え日本列島を放浪する情景を想像してみる。彼ら彼女らは世界をどのようにとらえていたんだろう?
本の中で、筆者と日本最後の琵琶法師、山鹿良之とのディスコミュニケーションの描写が印象的だった。
通常コミュニケーションというのは「視覚」によって焦点が合わされている。まさに目はカメラのレンズのように相手をとらえる。相手の表情から言葉以外のメッセージを受け取ることは自然に行われる。そもそも相手の顔を見ることで、意識の焦点がその人に結ばれ、声は聞きわけられ、周囲のざわめきは雑音として取りのぞかれる。
しかし、目が見えない相手の場合は通常のコミュニケーションの図式は成り立たない。視覚によって固定されることがないため、世界はざわめきに満ちたままで、意識は焦点が合わないまま様々な人物(過去や今の自分、他人や物語上の人物)に成り変っていく。リキッドなままで世界を語ろうとすると人は詩や物語をつくるしかないのかもしれない。
目を瞑って、周りの音に耳を澄ますと、普段は聞こえない木々のざわめきや、雨が葉を打つ音、虫や鳥の鳴き声が身体の中に入ってくる。
5月の田舎の夜など、カエルの大合唱やヨタカの鳴き声で外がうるさくて眠れないくらいだが、じっと目を閉じて暗闇の中でそういう音を聴いていると不思議に心地いい感覚になってくる。
きっと、自分の身体と自然の境界があいまいになってくるのだろう。
一体どこまでが自分で、どこからが自然なのか。
自然の音が身体を震わせ、やがて混沌としたざわめきの中に私の意識は解放される。
そして、もうすぐ世界と一体化することができそうな予感を感じつつ眠りに落ちる。
クラシックの演奏でも、本当にノッたときには、自分というものが身体から抜け出して、拡散して、今弾いているのは私なのか、はたまたこれは現実なのか、過去なのか未来なのか、あいまいになって、ふわふわとした心地よさのなかで音楽に身をゆだねている、という瞬間がある。めったにその境地にはなれないけれど、その感覚を知っているから、また味わいたいから私は音楽を続けているのかもしれない。
たぶん、ダンスでも演劇でも、絵でもあらゆる芸術活動の中でその感覚はあるはずだ。
その、ふっと自分が抜ける感覚、遠くから後ろから自分を眺めているようになる感覚が、昔は苦手だった。
子どもの頃の私にとって、その感覚がやってくるのは決まって年1回のピアノの発表会の舞台上であり、意識がふわふわしながら弾いている間は気持ちがいいのだが、ふと我に返って、あれ、今どこ弾いてるんだっけ?と考えてしまうとミスをしてしまい、そのあとは身体がカッと熱くなってもう訳がわからずいつのまにか演奏が終わっている、というのが常だった。舞台上は気持ちがいいが怖い。
緊張とは全然違う、その感覚がやってくる前は皮膚がザワザワとする。どこかに引っ張られそうにもなる。
音大時代には私は意識を飛ばさずに、集中して演奏する、冷静に身体をコントロールすることを大事にしていた。
飛びそうになる感覚を抑え込む術も覚えた。でも、最近はまたその感覚を大事にしたいと思うようになっている。どこか夢見心地のまま、こちらとあちらを漂いながらただ音楽の流れに身を任せてみたい。
2021.5.25
内海恵