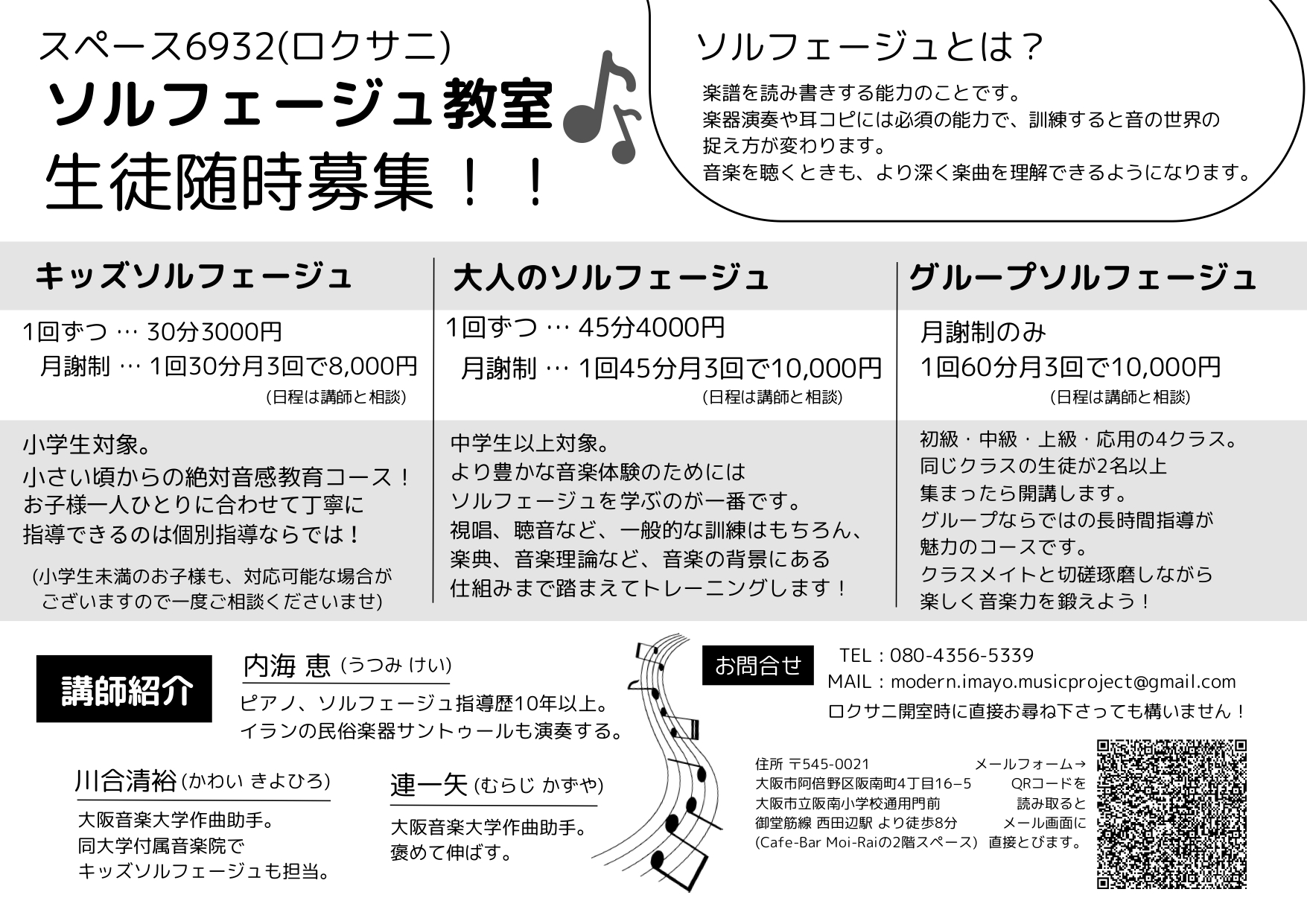赤と黄のコンポジション ~「サアディの薔薇」と「蜜柑」~
赤と黄のコンポジション
~「サアディの薔薇」と「蜜柑」~
マルスリーヌ・デボルド=ヴァルモール(1786-1859)という詩人がいる。
彼女は『サアディの薔薇』という代表作を歴史に残した。
当時のヨーロッパは東方への、熱病といってもいいくらいの憧れがあったのだ。といってもそれはリアルな東方に対してではなく、自分たちの想像を過分に重ねた幻想としての東方にである。まだ見たことのない世界があることへの興奮、新たな物語の源泉としての東方のイメージが、ヨーロッパには渦巻いていた。その熱はフィッツジェラルドの「ルバイヤート」によって頂点に達するように思われるが、ヴァルモールの詩が放つ甘い芳香はその中でも際立っていて多くの人を虜にする。
『サアディの薔薇』、これはもちろん13世紀のペルシャの詩人サアディの『薔薇園』からインスピレーションを得たものであるが、ヴァルモールはサアディのモチーフを借用し、夢想的で美しい愛の旋律を奏でてみせた。
私は今朝バラをあなたに届けたいと思いました。
でも締めた帯に余り沢山挟んだので、
きつく結びすぎた結び目は、たまらず
ぱっとほどけました。バラは風に舞って、
残らず海へと散って行きました。
潮に流され、もう戻っては来ませんでした。
波は赤く染まり、まるで火がついたよう。
今宵まだ私の服にはバラの香りがいっぱい・・・・・
私についたその香りの名残りを、お願い、吸って。
(安藤俊次訳)
溢れる想いが膨らみすぎて、零れ落ちていく様子が美しい。
ヴァルモールのインスピレーションを刺激したであろう部分は、サアディの『薔薇園(ゴレスターン)』の序文に現れる。
――物思いにふける聖者の一人が、頭を黙想の懐にもたせながら、幻想の海に浸っていた。やがて、われに帰ると、友人の一人が、うれしそうに言った。「君のさまよっていた花園から、どんな珍しいお土産を持って来てくれましたか」と。彼は答えた。「私が薔薇の繁みに着いたら、友人たちへのお土産に、花をすそ一杯に満たして来るつもりでした。しかし、私がそこに着くと、かぐわしい花の薫りが私を酔わしてしまったので、衣のすそが私の手から離れてしまいました。」(サアディ『ゴレスターン』より)
実際に薔薇は目の前にはないけれども、酔うほどの濃い薔薇の薫りが夢の中の秘密の花園から漂ってきそうだ。
どちらの詩でも赤い薔薇とその残り香の描写により、視覚と嗅覚が刺激される。帯がほどける、すそから手が離れる、という表現には肌感覚があり官能的な装いも感じさせる。
この詩を読んだときに、ハッと頭の中に浮かんだシーンがある。それは芥川龍之介の小説『蜜柑』の最後のシーン。田舎っぽい(そう描写される)女性が汽車の窓から身を乗り出して、持っていた風呂敷からたくさんの蜜柑をこぼれさせる場面だ。
――するとその瞬間である。窓から半身を乗り出してゐた例の娘が、あの霜焼けの手をつとのばして、勢よく左右に振つたと思ふと、忽ち心を躍らすばかり暖な日の色に染まつてゐる蜜柑みかんが凡そ五つ六つ、汽車を見送つた子供たちの上へばらばらと空から降つて来た。私は思はず息を呑んだ。さうして刹那に一切を了解した。小娘は、恐らくはこれから奉公先へ赴おもむかうとしてゐる小娘は、その懐に蔵してゐた幾顆いくくわの蜜柑を窓から投げて、わざわざ踏切りまで見送りに来た弟たちの労に報いたのである。 (芥川龍之介『蜜柑』より)
ある日私の頭の中で、結び目がぱっとほどけて薔薇が零れ落ち海を赤く染める『サアディの薔薇』と、汽車の窓からこぼれ出る『蜜柑』の色彩の美しさが瞬間的につながった。
これが「思考の手前の直感」だろうか。
燃えるような恋を表す赤い薔薇と、幼い兄弟たちへの贈り物である慈愛の蜜柑。
感情の違いはあるが、どちらも薔薇や蜜柑が女性の手から離れる瞬間の描写が美しい。
『蜜柑』は女性と同じ汽車に乗り合わせた男性の目線から語られる。
はじめ、男性は田舎っぽい女性を内心不快に思いながら観察していたが、女性がおもむろに立ち上がり、窓から風呂敷を広げ、パッと蜜柑を零れ落ちさせる瞬間を目にし、驚愕する。そして投げ出された蜜柑の先に女性の兄弟らしき幼い子供がいるのを窓越しに見て何とも言いようのない朗らかな気持ちになる。序盤の男性の鬱屈とした内面描写とは対照的に、暗い闇を切り裂く光のごとくラストシーンでは汽車の中には窓から清廉な風が入りこみ、蜜柑の爽やかな香りに胸を打たれる。
これと似た構造だなと思って、つい先日頭に浮かんだものがある。
太田道灌(どうかん)の「山吹伝説」だ。
室町時代の武将で歌人でもある道灌にはこんな逸話がある。
「鷹狩」に出て、にわか雨にあった道灌が、ある家で雨具の蓑(みの)を借りようとしたところ、その家の娘は黙って折ったヤマブキの一枝を差し出した。道灌は、花を求めたのではない!と怒って帰ってしまった。
しかし後になってそれは『後拾遺和歌集』にある、
「七重八重 花は咲けども 山吹の 実の(蓑)一つだに なきぞ悲しき」という兼明親王の歌にかけて、雨具の蓑一つさえない貧しい家なのだということを暗に伝えていたのだ、ということを知り(家臣から教えられたらしい)、自分の学の無さを恥じてそれから学問を志したという。
(八重ヤマブキには実がならない。雄しべは全て花びらに変化し花粉ができず、雌しべも退化しているため実がつかないのだ。挿し木などでしか繁殖できないという。色んな意味を付け足したくなる、なんて興味深い花なんだろう。)
この逸話では、女性が手に持つ雨に濡れたヤマブキのあざやかな黄色が脳裏に浮かぶ。それが芥川の『蜜柑』と繋がるのだ。双方とも貧しい女性の心意気に打たれる男の様子を描いている。ヤマブキが、蜜柑が、乾いた心に暖かな火を灯す。
もう一つ、芋ずる式に頭の中に檸檬が浮かんだ。
そう、あの本の上に置かれた檸檬である。
しかし梶井基次郎の『檸檬』では、少し様子が異なってくる。
太田道灌は実際に貧しい娘とコミュニケーションをしている。(娘は無言だが)
『蜜柑』に出てくる青年は、会話はしないが田舎娘を仔細に観察し、行動を見ることで自らの感情を振り動かされる。
梶井の『檸檬』はもっと閉じた世界である。その世界には自分を揺り動かす他者は存在しない。自分の悩みや葛藤、孤独で埋め尽くされた世界はやがてその内圧に耐え兼ね爆発する。檸檬は美しい心を持った女性の手ではなく、孤独な青年の手により本屋の片隅に置かれ、爆発することなくしぼんでいくだろう。モラトリアムな梶井の檸檬。
閉じた世界もいいのだが、、誰かを思って心震わすことの充足感を知ると、月並みな言い方になってしまうが自分の世界が広くなる。閉じていた扉が開かれ風が入ってくる。扉を出ると庭園で、月に照らされた薔薇の下でナイチンゲールが鳴いている。
最後にもういちど、ヴァルモールの『サアディの薔薇』について。
この中に出てくる、「ぱっとほどける」という表現。元のフランス語は独特のニュアンスを出しており、翻訳するのが中々難しいらしい。ぱっとほどける、、持っていたものが零れ落ちる、ほどける、すそから手が離れる、、。
以下は私の勝手なイメージなのだが、、
先日金曜ロードショーで「タイタニック」の後編を見た。
最後の場面で、年老いたローズが船から海面を見下ろし、おもむろにダイヤモンドのネックレスを海に落とすシーンがある。「っ」という小さな高音のスタッカートの声とともに海に沈む思い出のネックレス。。ああいう風に身体から離れていく感覚がヴァルモールの詩にもあるかもしれないな、とこっそり思っている。
薔薇のことを考えているうちに、蜜柑、檸檬、山吹、タイタニック、と勝手にイメージが繋がり、頭の中で赤と黄のコンポジションが出来上がっていった。
そこでは身体から大事なものや意識が離れる浮遊の感覚が共通しているような気がする。
(参考文献)
山中哲夫『花の詩史』大修館書店 1992年
サアディ著 澤英三訳『ゴレスターン』岩波書店 昭和26年
芥川龍之介『蜜柑』 青空文庫
梶井基次郎『檸檬』 青空文庫
片岡寧豊『万葉の花』青幻舎 2010年
2021.5.19
内海 恵